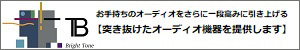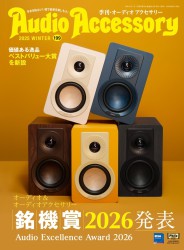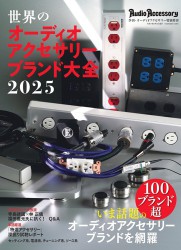エソテリックのシステムでオーケストラのオーディションを実施。指揮者・佐渡 裕氏が新しい才能を発見
オーディオシステムで演奏を再生するというオーディション
通称PACオーケストラの名で知られる兵庫芸術文化センター管弦楽団は演奏家の育成を目標のひとつに掲げるアカデミーの要素を持つプロオーケストラで、2005年の創立以来、関西を中心とした音楽ファンの熱い支持を集めている。

在籍期間が最長3年と定められているので毎年メンバーの約3分の1が入れ替わり、新たな団員を採用するためのオーディションが定期的に開催される。すみだトリフォニーホールの練習室1で行われたそのオーディションの現場を取材する機会があったので、ご紹介しよう。

当日は同オーケストラの芸術監督をつとめる指揮者の佐渡 裕さん、コンサートマスターの田野倉雅秋さんによる最終審査が行われたのだが、会場にはオーディション参加者の姿はなく、審査員の前にはオーディオシステムがセットされていた。あらかじめ行われた二次審査で録音された音源を再生しながら審査を進めるのだ。
田野倉さんは二次審査でも審査員を務めているので応募者の演奏に接しているが、佐渡さんが演奏を聴くのはこの日が初めてだ。エソテリックのネットワークプレーヤー「N-05XD」とプリメインアンプ「F-01」、それにタンノイの「SGM 10」を組み合わせたシステムで、まずはヴァイオリンパートの採用候補を絞り込む。


SGM 10から流れるヴァイオリンの音色や表情には一人ひとり個性があり、演奏者の動きが目に見えるようなリアルな音が浮かぶ。課題曲は協奏曲の独奏パート、交響曲の第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンの抜粋など多岐にわたる。
どんな基準で評価を進めるのか、審査終了後に佐渡さんに尋ねてみた。「曲ごとに適切な演奏スタイルで弾いているかどうかを重視します。もちろん音色やテンポ感も重要な点です。オーケストラのなかで周りを聴きながら演奏できるかという点も大事ですね」。
最長3年間という限られた期間ではあるが、PACでの演奏経験は団員一人ひとりにとって大切な意味を持つ。PACの活動を終えた後はプロオーケストラ、ソリスト、教育機関など進む道はそれぞれだが、どの道を選んでもコンサートでの演奏経験が糧になるのだという。
「大ホールの収容人数は約2000人。しかも定期演奏会は3日間続けて公演を行います。大きなホールを埋める満員のお客さんを前に演奏する経験は団員にとってかけがえのないものなんです。感動はもちろん、失敗も含めてPACで重要な経験を重ね、その経験が、日本を代表するオーケストラのメンバーになったときにも、とても役に立つんです」(佐渡さん)。


 PACコンサートマスターの田野倉雅秋氏。氏はこのひとつ前に行われた二次選考会で生演奏を聴いて審査を行っている
PACコンサートマスターの田野倉雅秋氏。氏はこのひとつ前に行われた二次選考会で生演奏を聴いて審査を行っている
それぞれの楽器の長所がどこまで見えてくるかが重要
録音された音源を聴いて審査するうえで、楽器によって判断のしやすさが変わるものだろうか。「特に難しいなと感じるのは打楽器ですね。同じ距離で録ると振り切れてしまうぐらい音量が大きく、余韻が広がる空間も大きいですから。再生システムの違いは、それぞれの楽器の長所がどこまで見えてくるか、という点に現れると思います。たとえばチェロなど、倍音を豊かに再現するととても立体的な音になります。今日のシステムはそこがとてもよくわかりました」(佐渡さん)。
佐渡さんがオーディオ装置で音を聴くとき、どんな点を意識しているのか、尋ねてみた。「プライベートで兵庫、東京、ウィーンなど複数の場所でそれぞれ特徴的なシステムを使っています。オーディオシステムで特に意識して聴くのは、オーケストラのいろいろな楽器を正確に再現できるかどうかという点ですね。特定の音域に音が集中したり、ティンパニの音がこもって聴こえるような音は好ましくないと思います。クラシックだけでなく、ジャズも良く聴くんですよ。マイクがオンで楽器の音像の大きさなどもチェックしやすいですから。ディスクプレーヤーはエソテリックの製品が気に入っていて、自宅でも使っています」(佐渡さん)。


倍率が数百倍に及ぶこともあるというプロのオーケストラのオーディション。その厳しい審査環境において、オーディオ機器が重要な役割を演じていることがわかり、とても興味深い取材となった。厳しい審査をくぐり抜けた演奏家がPACのステージデビューを飾る日は近い。
(Photo by 君嶋寛慶)
関連リンク