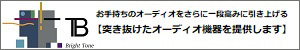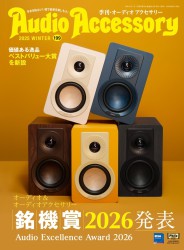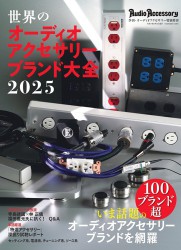【HIGH END】JBLが“SUMMITシリーズ”を出した狙いは?その音質は?オーディオ評論家・山之内 正氏が迫る!
ミュンヘンのハイエンドショウで、JBLがサミットシリーズの新製品3モデルを発表した。「Makalu」「Pumori」「Ama」の命名ロジックはProject EverestやProject K2に連なるもので、それぞれヒマラヤ山脈の峻峰マカルー、プモリ、アマに因む。特にマカルーの険しさは抜きん出ているが、そこに標高一位と二位に君臨するエベレストとK2が入っていないという疑問が浮かんだ。

その答えは一つしかない。新しいサミットシリーズはこれで完結ではなく、全貌はまだ明かされていないということだ。JBLは創立60周年にあたる2006年に「Everest DD66000」を発売した。その事実から、新世代のEverestとK2は創業80周年を迎える2026年に登場すると予測するのが順当だろう。今回発表された3機種が次世代フラグシップの技術やデザインの一部を先行して投入しているという予想も成り立つ。
少し昔の話をすると、DD66000発表時の衝撃はいまも忘れられない。前面と背面いずれも大きく湾曲したプロフィールと家庭用スピーカーとしては最大級のエンクロージャーに巨大なホーンと38cmウーファー2基を積んだ構成は斬新きわまりないが、よく見ると、パラゴンの優美な曲面構成、4350やEverest DD55000のドライバー構成など、歴代フラグシップの設計手法を連綿と受け継いでいる。JBLの根幹の哲学は変わっていないのだ。そのことに気付いた瞬間、原点を意識しながら新たな高みを目指すことにJBLの強みがあることを確信した。
当時、DD66000の開発を担ったキーパーソンは、1985年に登場したEverest DD55000と同じ二人、エンジニアのグレッグ・ティンバースとデザイナーのダニエル・アシュクラフトである。2006年にノースリッジのJBL本社を訪れたとき、彼らがDD66000の詳細を熱く語っていたことを思い出す。他に例のないディメンジョンや大きく湾曲したエンクロージャーに新しい方向を感じたことを告げると、「家庭用スピーカーの頂点をきわめることを目指した結果、この形に行き着きましたが、革新的なDD66000にもJBLの歴代スピーカーの設計思想が生きているのです」と二人揃って明言したことをよく憶えている。伝統と革新という2つのベクトルが根幹にあるということだ。
DD66000からDD67000へと受け継がれた流れは後者の生産完了でいったん停止するが、これまでのJBLの歩みを振り返れば、そこで止まることは考えられない。設計陣の世代は変わっても、設計思想の根幹が揺らぐことはないはずだ。
伝統を受け継ぎながらも次世代を見据えて大胆に変えることも辞さないのがこれまでのJBLのスタイルだ。今回発表されたサミットシリーズの3機種に目を向けると、重要な「革新」の要素を見出すことができる。
上位2モデルにミッドレンジを追加したことがまずは大きな変更点だ。Makalu、Pumoriどちらもメーカーはミッドバスと呼んでいるが、低音だけでなく、ヴォーカル帯域の一部を含む中低域から中高域にかけてのスムーズなつながりを狙っているとみるのが妥当だろう。

Makaluは30cm、Pumoriは25cmというウーファーの口径の違いはあるが、ミッドバスはどちらも20cm口径で共通。鋭敏で制動が効いた低音を確保しつつ、音圧感と量感も半端ではない。質感の高い低音は声や主要旋律の音域での見通しの良さと浸透力の強さにつながり、抜けの良さは特筆に値する。MakaluとPumoriどちらも新世代のJBLを象徴する名機となる可能性を秘めていると感じた。
フラグシップのレンジで初のブックシェルフ型となるAmaの再生音は、上位2機種の長所に加えて20cmウーファーならではの俊敏な低音を獲得していることで、ベースとホーン楽器が同時に立ち上がることで生まれる聴感的な音圧の大きさに強い印象を受けた。速さと音色を高次元で揃えており、一言で表せばストレスのない爽快なサウンドを繰り出すのだ。コンパクトなスピーカーだが音のインパクトは強靭で、コンプレッションドライバー+ホーンならではの抜けの良い中高域にJBLらしさを強く実感した。

3機種いずれも正式な価格と導入時期は未定だが、この後にフラグシップの登場を控えていると仮定したうえで、極端な高価格にならないことを期待したい。日本では秋のインタナショナルオーディオショウで公開予定とのことなので、来年には全貌が明らかになると思われる80周年記念モデル群への期待を込めながら、まずはサミットシリーズ3モデルの正式ローンチを待つことにしよう。

余談だが発表会で一番長いスピーチを展開したベネディクト・ベームは、アルパインスタイルと呼ばれる尖鋭なアプローチで知られる登山家だ。最小装備での未踏ルートへの挑戦や山頂からのスキーでの長距離滑降が得意なようだが、その経験をビジネスに活かすというユニークな持論の持ち主でもある。
高度順応の意味や極限まで装備を削ぎ落とすことの重要性を生死の境界線をくぐり抜けた経験を交えて語るので、たしかに説得力があり、同席したJBLのキーパーソンたちもしきりに頷いていた。新たな頂点を未踏ルートから目指す次期フラグシップにも尖鋭なアプローチが隠されているに違いない。
関連リンク
トピック