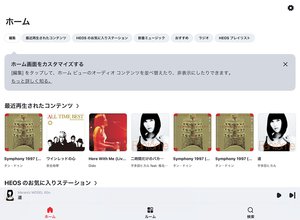PRマランツとB&Wの「基本セット」からそれぞれグレードアップ
オーディオのグレードアップ、どこから手をつけるべき?スピーカー、アンプ、ケーブル交換の効果を実践テスト!
■音質グレードアップの考え方の基本を学ぼう
現在の自分のオーディオシステムの音に満足しているならもちろん何も換える必要はない。余計なことはせず、気に入っている音で存分に音楽を楽しむまでのこと。しかしもし具体的な不満を、あるいは、まだはっきりと言語化できるレベルではないにせよ、音に何かしら違和感を覚え始めていたとしたら?
限りある時間にせっかく音楽を聴くのに、音が気になって楽しめないというのは悲しいことだ。やはりこの場合、システムのグレードアップを図る必要があると言えるだろう。
ではグレードアップを図る場合、実際どこから手をつけるのか? やはりスピーカーを上位機に? いやその前にアンプの方を? はたまたアンプとスピーカーはそのままに、ケーブル等のアクセサリーを投入する? ここは意外に悩むところである。
そこで今回は、スタート地点となる基本システムを設定し数曲試聴してから、スピーカー、アンプ、ケーブルをそれぞれ換えたら具体的にどう音が変わるのか、実験してみようと思う。グレードアップのご参考になれば幸いだ。
■スピーカー+プリメインアンプの基本セットからどう攻める?
今回は基本システムとして、アンプにはマランツのHDMIセレクター搭載Hi-Fiステレオプリメインアンプ「STEREO 70s」(143,000円/以下すべて税込定価)、スピーカーにはB&W「607 S3」(132,000円)をチョイスした。合計すると275,000円。どちらも市場で人気の製品である。
プリメインアンプ「STEREO 70s」はプリアンプ回路に、マランツ独自の高速アンプモジュール「HDAM-SA2」を用いた電流帰還型回路を採用。これにより繊細かつ情報量の豊かなサウンドを実現。さらに定格出力75W+75W(8Ω)のフルディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ回路に電源を供給するブロックコンデンサーにはなんと「STEREO 70s」専用にサプライヤーと共同開発したカスタムコンデンサー(6,800μF×2)を採用。さらに電源トランスには大型カスタムEIコアトランスを採用することにより、高品位で安定した電源供給を実現している。
スピーカー「607 S3」は新開発のチタニウム・ドーム・トゥイーターに、正確性と透明性で評価の高いコンティニュアム・コーンを組み合わせている。トゥイーターにはB&Wのフラグシップ「800 Series Signature」用に開発された、音響的な透明度が向上した新しいトゥイーター・グリル・メッシュを導入。
この組み合わせで、HEOSアプリを使ってAmazon Musicで数曲聴いてみよう。
基本システムの音調を試聴曲ごとに具体的に述べれば、まず宇多田ヒカル「二時間だけのバカンス」はワイドレンジ感をいたずらに強調せず、各音の温度感はほんのり温かめ。Dido『Live at Brixton Academy』はライブ会場が少々こじんまりする反面、親密な空間と時間が眼前で展開するようで気持ちいいが、ギターの質感がやや硬いか。
タン・ドゥン『交響曲1997「天、地、人」』も大きな録音会場に何百人もの奏者がいるはずなのだが、会場の広さと演奏規模が比較的コンパクトに描写されるからか大仰な雰囲気が抑えられて、聴き手をリラックスさせる再生音だ。リビングで会話を楽しみながら、上質な音で奏でられる音楽を寛いで聴くといったシーンがこの音から思い浮かぶ。
さて、いよいよグレードアップ実験スタートである。
■プラン1.スピーカーのグレードアップ
まずはスピーカーを「607 S3」から上位機「707 S3」に換えてみよう。約15万円の価格アップである。「707 S3」はカーボンドーム・トゥイーター、そして「607 S3」同様のコンティニュアム・コーン・ミッドバスを搭載している。
結論1.キャビネットの制振対策によりS/Nが向上
結論2.トゥイーター性能による情報量の増加
結論3.解像度が上がり音場再現力が高まる
まずはスピーカーを「607 S3」から上位機「707 S3」に換えてみよう。約15万円の価格アップである。「707 S3」はカーボンドーム・トゥイーター、そして「607 S3」同様のコンティニュアム・コーン・ミッドバスを搭載している。
カーボンドーム・トゥイーターは700シリーズ専用に設計されたものだ。従来のアルミニウム・ダブルドーム・トゥイーターに改良を加え、共振周波数を47kHzまで引き上げている。これに加えて回折を考慮してカーブさせたフロントバッフルを採用したことにより、高い解像度だけでなく、優れた音場表現能力と、各音像への焦点がピンポイントに定まる正確なフォーカス性能をも得ている。
宇多田ヒカルが冒頭からまるで違う。ノイズフロアがググッと下がって静かな音場に、宇多田ヒカルが最初に息を吸う音がその音像の正確な位置とサイズを伴ってはっきりと聴き取れる。同じくさっきはぼやけて暗騒音に紛れていたテープヒス調の背景音も、やはり正確な位置とサイズを伴って容易に聴き取れる。
アンプではなくスピーカーのグレードアップで解像度と音像定位の向上だけでなく、ノイズフロアの低下までをも実現してしまったことに、あるいは不思議を覚える方がいらっしゃるかもしれない。しかし「スピーカーキャビネットのS/N性能」というものがある。スペック表にこそ表示されなくとも、グレードがより高いスピーカーのキャビネットには、下位グレードのスピーカーにはコスト的に採用が難しいハイレベルな制振性能を備えた構造や素材を導入する例が多い。せっかく下位グレードより優れたユニットを搭載しても、ユニット由来の振動をキャビネットが素早く処理できないと、その振動がユニットに戻って、せっかく向上した解像度だけでなくS/Nをも損なってしまうからである。
Didoはギターの質感がさらに硬めに。しかしドラムスそして聴衆の歓声や口笛、ざわめきの解像度は激増。ヴォーカルの音像が引き締まる。ギターも音像によりピントが合いサイズがコンパクトになる。これらはトゥイーターの性能向上による情報量の増加と、カーブされたフロントバッフル面が回折による音波干渉を減少させたことの賜物だろう。
タン・ドゥンはチェロの解像度が桁違い。胴鳴りが精緻かつ深い。鐘の余韻と児童合唱が綺麗に分離する。
基本システムでは「ながら聴き」ができたが、スピーカーをグレードアップしたら「おっ!これはいったん会話を止めて再生音に真剣に耳を傾けねば!」と思わせる音になった。たとえるならそういう変化だ。
やはりスピーカーのグレードアップはモロに音に効く。再生音のクオリティに決定的な影響力を持つのは、音楽信号を空気の振動に変換するスピーカーだと、改めて痛感する。ユニット自体の解像度と、キャビネットの制振性能そして回折対策とが、解像度とS/N、そして音場・音像表現力にダイレクトに関わるのだ。
■Plan2.スピーカーケーブルのグレードアップ
ではアンプとスピーカーの基本セットから、スピーカーケーブルだけ安価な切売からaudioquestの「Rocket 11」に換えるとどうなるか?
結論1.導電性の向上により解像感がアップ
結論2.高周波ノイズの抑制によりスピード感や質感が向上
結論3.バイワイヤリング接続でユニット性能がさらに引き出される
「Rocket 11」は導体が高純度銅半撚り単線(PSC) と半撚り銅単線(LGC)。絶縁体はPVC。カーボンベースノイズディシペーションにより高周波ノイズを消散させる。今回はスピーカー側がバイワイヤー対応となっているため、バイワイヤ仕様をチョイスした(なお、Rocket 11はシングルとバイワイヤ製品で価格は共通)。
基本セットでは安価な切売ケーブルをシングルワイヤーで接続していたので、今回はケーブル自体の性能アップに加えてバイワイヤリングによる性能アップをも得られることになるが果たして結果は?
宇多田は冒頭の息を吸う音と背景音がより精緻に。音像周囲のS/Nが大幅に向上。音像自体は立体感と密度感が高まっている。パーカッションの歯切れがいい。静かになった音場に各音が精密に解像されているのでもっと細かい音を聴くために音量を上げる必要を感じない。そして(実はずっと気になっていた)ストリングスの、キンキン鳴ってチープだった質感が随分と改善して滑らかで上質なものに。椎名林檎と宇多田ヒカルのヴォーカルは綺麗に分離したうえでハモっている。
「Rocket 11」の価格は56,100円(3m)。スピーカー本体のグレードアップよりは安価ながら、当初の切売ケーブルでは引き出せなかったスピーカーの本領を発揮させてくれた。導体の導電性が高まり、導通に必然的に伴う高周波ノイズが抑制され、さらに今回はバイワイヤリング接続により高域が低域の大きな磁界の影響を受けなくなった効果も加わって、解像度とS/N、スピード感、質感が向上したのである。
■Plan3.アンプのみのグレードアップ
では今度は、スピーカーは「607 S3」に戻して、アンプを「MODEL 60n」にグレードアップしたらどうなるか聴いてみよう。価格は約10万円のアップ。スピーカーケーブルも当初の安価な切売に戻す。
結論1.電源部のレベルアップにより密度感や力感が向上
結論2.チャンネルセパレーションの向上により音像がより立体的に
結論3.低域をよりパワフルにドライブする
「MODEL 60n」は「STEREO 70s」同様AB級アンプ。一般的に使用される音量の範囲内ではプリアンプでの増幅を行わず、パワーアンプのみで増幅する可変ゲイン型を採用してノイズレベルを大幅に改善。
ボリューム部には、チャンネル間のクロストークとギャングエラーを最小化するため、可聴帯域外に至るまで優れた特性を備えるボリュームコントロールICを採用。これに高速アンプモジュール「HDAM」と「HDAM-SA2」を組み合わせてリニアコントロールボリューム回路を構成する。
パワーアンプには、ハイスピードでS/Nが高く、低歪率な「HDAM-SA3」を用いたフルディスクリート構成の電流帰還型増幅回路を採用。
電源回路には、クリーンな電流を安定的に供給し、かつ瞬間的な大電流の要求にも耐えられるようシールドケース付きの大容量トロイダルトランスを搭載。漏洩磁束を抑えるため、垂直方向の磁束漏れを抑えるアルミ製ショートリングに、水平方向の磁束漏れを抑える珪素鋼板シールドを加えた2重シールドを施している。また、平滑回路には本機用に開発されたカスタムブロックコンデンサー(15,000μF/63V)を採用し、大容量と高速な電源供給能力を両立させている。
結果、定格出力こそ「STEREO 70s」の75W+75W(8Ω)に対して「MODEL 60n」のそれは60W+60W(8Ω)と見かけ上は及ばないものの、電源部が質・量ともに大きくレベルアップしているぶん、実ドライブ力は「MODEL 60n」の方が上回る。実際に聴いてみよう。
同じ「607 S3」をドライブさせても、アンプが「STEREO 70s」のときには聴き取れなかった宇多田ヒカルが最初に息を吸う音と背景音が、「MODEL 60n」だと聴こえる! これはスピーカーではなくアンプの側の解像度向上とS/N向上の賜物だ。
そして電源部の余裕とチャンネルセパレーションの向上がてきめんに効いているのだろう、ヴォーカルが密度感と、上下左右だけでなく前後方向にも立体感を大いに高めたので、音像が手前方向、すなわち聴き手側に寄る。ベースは筋肉質になって力強い。ドラムスはメリハリが立つ。しかし「STEREO 70s」でドライブしたときと同様、広過ぎないレンジ感とほんのり温かい温度感には変化がない。これは「607 S3」の個性なのだろう。
Didoはずっと気になっていたギターの質感の耳障りな硬さがやっと解消。さらに、歓声が奥方向に移動する形で演奏会場に広さが出た。ギターもヴォーカルも音像の周囲が静かで聴き取りやすい。歓声や口笛、ヴォーカルや各楽器の解像度が「707 S3」ほどではないもののだいぶ上がっている。
驚いたのはタン・ドゥン。他の試聴曲と違い電子音を使わないこの曲では、鐘や太鼓や合唱等から発せられる自然音の倍音成分が「STEREO 70s」のときよりはるかに細やかに再生されるからであろう、音の品位が随分と上がっている。さらに電源部の余裕度アップが一音一音の力感を増大させ、音楽全体を支える低域の重厚感と安定感をも高めている。
やはりスピーカーでなくアンプの方をグレードアップすると、スピーカーの挙動をより正確に制御できるようになるからであろう、実ドライブ力不足がもたらしていた特定帯域の不自然な質感は消え、全帯域で力感が増す。高い実ドライブ力が必要なウーファーもより一層制動を効かせながらパワフルにドライブする。加えてチャンネルセパレーションの向上により音像の立体感や音場表現力さえもが高まるようだ。なるほど、一見するとたしかにスピーカーやスピーカーケーブルのグレードアップとかぶる音質向上効果がけっこうあるようにも思えるが、特にチャンネルセパレーションばかりはスピーカーやスピーカーケーブルのグレードアップでは変えようがあるまい。
■Plan4.合わせ技!アンプとスピーカーのグレードアップ
では今度は、アンプはこのまま「MODEL 60n」として、スピーカーを「707 S3」に換えてみよう。どう変わるか?
スピーカーとアンプそれぞれのS/N向上が相乗しているのだろう、宇多田のノイズフロアがきわめて低い!そしてヴォーカル音像がギュッと引き締まり密度感アップ。パーカッションやベースの歯切れがいい!宇多田によるバックコーラスが鮮明かつ克明。
Didoは冒頭の拍手が多い。これも、スピーカーとアンプそれぞれの解像度向上が相乗しているからに違いない。会場からは暗騒音が消えた。「607 S3」のときより高域はグッと伸びたが、アンプの制動力も増しているので質感上の違和感はない。
タン・ドゥンも全楽音の解像度アップ。鐘の倍音が精緻。各音像の周囲が静か。太鼓が空気を揺さぶるさまが強くて克明。
■Plan5. 究極の合わせ技!アンプ、スピーカー、スピーカーケーブル全てのグレードアップ
最後にPlan4の状態から、スピーカーケーブルをグレードの高いaudioquest「Rocet 44.2」に変更してみよう。導体が高純度銅単線(PSC+)と銅単線(PSC)。絶縁体はフォームドポリエチレン。カーボンベースノイズディシペーションによるノイズ消散は「Rocket11」と同様である。
宇多田は背景音の解像度が激増。宇多田のブレスがさらに静けさを増した周囲とのコントラスト効果できわめて生々しい。ヴォーカルと伴奏との混濁激減。ストリングスの質感と音色が大幅に品位アップ。
Didoは左右のスピーカーの周囲の音場にも前後。今まで中央にしか前後がなかった。ここにきて初めて聴こえた電子音がいくつもある。印象派絵画が写真になったとまで言ったら大袈裟か?
タン・ドゥンはリアルな空気感が出た! チェロの胴鳴りが実に実に彫り深い。鐘の余韻は消えるまで精緻。児童合唱のテクスチャーが極上。各鐘の大小=音域の違いが解像度と立体感を増した音で歴然………。
グレードアップ実験、いかがだったであろうか。
以上の実験から「スピーカー・アンプ・ケーブルそれぞれの内容・機能・性能が再生音に具体的にどう影響するか」を理解・把握すれば、ご自身のシステムに不満を抱いたときどう対処すればよいかが相当程度見えてくることだろう。ぜひ手元のシステムのグレードアップの参考にしていただければ幸いだ。
(提供:ディーアンドエムホールディングス)