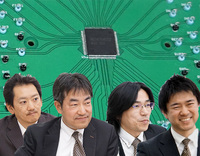【PR】開発陣に詳細を聞いた
構想10年、DACを2チップに“分離”した成果とは? AKM「AK4191+AK4498」を聴いた
2020年3月、旭化成エレクトロニクス、AKMから新たなDACソリューションが発表された。
現在のDACチップはΔΣ変調を利用した1〜複数bitのD/A変換をワンチップで完結するものが主流だが、AKMが新たに提案するのは、DACチップの中のデジタルセクションとアナログセクションを完全に分離し、2チップ構成でDACの役割を担う、いわばセパレート構成のソリューションだ。
その第一弾として、デジタルフィルターとΔΣモジュレーターを担うデジタル処理用の「AK4191」と、D/A変換のみを担う「AK4498」が今回登場した。
AK4191は1536kHz/64bit・PCM&45.1MHz・DSDまでの入力に対応し、オーバーサンプリングレートについても従来の8倍フィルタリング処理から256倍へと大幅にスペックアップ。デジタルフィルターの抑圧量となる阻止帯域減衰については、従来から50dB上げた150dBを実現した。
一方のAK4498は「AK4497」をベースとした電圧出力型となっており、フラグシップDAC「AK4499」と同じ電気的な余裕度と低域ノイズ特性を大幅に高めたオーディオ専用ICプロセスを採用している。S/N比は128dB、高調波歪率は−116dBとなり、こちらはAK4497に準じるスペックだ。
AKMでは2018年末、これまでの歩みを統括する電流出力型のフラグシップDAC、AK4499を発表した。S/N比が140dB、高調波歪率が−124dBという他社を圧倒する驚異的なスペックが話題となったが、そのサウンドの精緻さ、空間表現のリアルさも従来モデル以上のクオリティを実現し、DACチップにおけるAKMの存在感をさらに高めたのである。
それでは、今回登場したセパレートDACソリューションはどのような経緯で誕生したのか。
80年代から90年代にかけてのDACにおいてはデジタルフィルターを担うチップとマルチbitのDACチップを組み合わせた2チップ以上の構成のものも多く見かけたが、そうした製品群やこれまでのワンチップ型DACの流れとは異なる意図、方向性を持たせた特別なアイテムであることには違いない。デジタル/アナログ完全分離のAK4191+AK4498開発の経緯について、リモート環境にてAKMの開発陣にお話をうかがうことができた。
まずユニークなセパレートDACの開発に至るきっかけについて、旭化成エレクトロニクスのマーケティング&セールスセンター ソリューション第1部、オーディオマイスターの佐藤友則氏、そして製品開発センター 製品開発第1部の中元聖子氏に聞いた。
オーディオマイスターの佐藤友則氏はこう語る。
「AKMは1989年からΔΣDACのBtoB販売を開始し、実績を積みました。1990年代にはS/N比が120dBに到達し、しばらく数字競争の時代が続きます。私は1998年に入社しましたが、オーディオが好きだったこともあり、数字競争より『音を良くしたい』という思いの方が強かったですね」。
「その思いは2007年、32bit DAC『AK4397』に結実するわけですが、一方でライバルモデルと負けないスペックを持つことも必要であり、その後の『AK4490』、そしてオーディオ専用のLSIプロセスをアップデートした『AK4497』、さらに特性を高めた『AK4499』を生み出してきました。音質、スペックともにAK4499でやり切ったという思いですが、しかし、これまでのワンチップDACという枠の中で解決できていなかったことがあったのも事実です。この課題の一つが、デジタル処理とアナログ処理の分離というポイントでした」。
現在のDACチップはΔΣ変調を利用した1〜複数bitのD/A変換をワンチップで完結するものが主流だが、AKMが新たに提案するのは、DACチップの中のデジタルセクションとアナログセクションを完全に分離し、2チップ構成でDACの役割を担う、いわばセパレート構成のソリューションだ。
その第一弾として、デジタルフィルターとΔΣモジュレーターを担うデジタル処理用の「AK4191」と、D/A変換のみを担う「AK4498」が今回登場した。
AK4191は1536kHz/64bit・PCM&45.1MHz・DSDまでの入力に対応し、オーバーサンプリングレートについても従来の8倍フィルタリング処理から256倍へと大幅にスペックアップ。デジタルフィルターの抑圧量となる阻止帯域減衰については、従来から50dB上げた150dBを実現した。
一方のAK4498は「AK4497」をベースとした電圧出力型となっており、フラグシップDAC「AK4499」と同じ電気的な余裕度と低域ノイズ特性を大幅に高めたオーディオ専用ICプロセスを採用している。S/N比は128dB、高調波歪率は−116dBとなり、こちらはAK4497に準じるスペックだ。
AKMでは2018年末、これまでの歩みを統括する電流出力型のフラグシップDAC、AK4499を発表した。S/N比が140dB、高調波歪率が−124dBという他社を圧倒する驚異的なスペックが話題となったが、そのサウンドの精緻さ、空間表現のリアルさも従来モデル以上のクオリティを実現し、DACチップにおけるAKMの存在感をさらに高めたのである。
それでは、今回登場したセパレートDACソリューションはどのような経緯で誕生したのか。
80年代から90年代にかけてのDACにおいてはデジタルフィルターを担うチップとマルチbitのDACチップを組み合わせた2チップ以上の構成のものも多く見かけたが、そうした製品群やこれまでのワンチップ型DACの流れとは異なる意図、方向性を持たせた特別なアイテムであることには違いない。デジタル/アナログ完全分離のAK4191+AK4498開発の経緯について、リモート環境にてAKMの開発陣にお話をうかがうことができた。
まずユニークなセパレートDACの開発に至るきっかけについて、旭化成エレクトロニクスのマーケティング&セールスセンター ソリューション第1部、オーディオマイスターの佐藤友則氏、そして製品開発センター 製品開発第1部の中元聖子氏に聞いた。
オーディオマイスターの佐藤友則氏はこう語る。
「AKMは1989年からΔΣDACのBtoB販売を開始し、実績を積みました。1990年代にはS/N比が120dBに到達し、しばらく数字競争の時代が続きます。私は1998年に入社しましたが、オーディオが好きだったこともあり、数字競争より『音を良くしたい』という思いの方が強かったですね」。
「その思いは2007年、32bit DAC『AK4397』に結実するわけですが、一方でライバルモデルと負けないスペックを持つことも必要であり、その後の『AK4490』、そしてオーディオ専用のLSIプロセスをアップデートした『AK4497』、さらに特性を高めた『AK4499』を生み出してきました。音質、スペックともにAK4499でやり切ったという思いですが、しかし、これまでのワンチップDACという枠の中で解決できていなかったことがあったのも事実です。この課題の一つが、デジタル処理とアナログ処理の分離というポイントでした」。