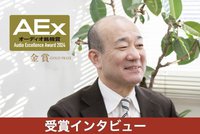【インタビュー】XGIMIでライフスタイルがもっと豊かに。スマートプロジェクターの魅力をさらに広げたい
VGP2025受賞インタビュー XGIMI
ホームプロジェクター出荷量世界No.1を誇るXGIMI。グローバルビジネスの指揮を執るTex Yang氏は、お客様から寄せられた「プロジェクターってこうやって使うんだ」という声が心に強く残っていると話す。「ユーザーのライフスタイルをより豊かにするような製品を作りたい」と力を込めるYang氏に、ホームプロジェクター市場創造への意気込みを聞く。

XGIMI Technology
グローバルビジネス事業担当
副社長
Tex Yang氏
2019年にグローバルセールス&マーケティング担当副社長として入社し、グローバルビジネス開発を担当。XGIMI入社以前は、ルクセンブルクのVodafone Procurement Company(欧州No.1通信事業者)およびドイツのHuaweiで上級管理職を務め、サプライチェーン、セールス、マーケティング分野で20年以上の経験を有する。
「MoGo 3 Pro」のコンセプトは「見てよし・聴いてよし・遊んでよし」
―― VGP2025におきまして、XGIMI「MoGo 3 Pro」がパーソナルビジュアル大賞を受賞されました。おめでとうございます。これまでのプロジェクターの概念を打ち破る、ライフスタイルを広げる商品として審査会でも高い評価を集めました。
Yang ありがとうございます。今回、この「MoGo 3 Pro」の企画、商品化にあたっては、「見てよし」「聴いてよし」、そして「遊んでよし」という3つのコンセプトを掲げて取り組みました。

―― 聴いている音楽のテンポに合わせて光る「スピーカーライトモード」、幻想的なプラネタリウムの映像やVR体験で日常の空間をより楽しい特別な空間にするマジカルレンズをはじめ、五感やライフスタイルに訴える数多くの提案が盛り込まれています。
Yang 今日の製品に至るXGIMIの歴史について少しお話しさせてください。当初の製品を振り返ると、スペックや性能が前面に打ち出されており、デザインやカラーバリエーションにもテクノロジー感、ガジェット感が強く表れていました。また、海外市場に対する認知もまだまだ十分なものではありませんでした。
欧米のユーザーの方々からのフィードバックを見ても、テクノロジーが好き、ガジェット好きといった方に多くご愛用いただいていることがわかります。その中でも強く印象に残っているのが、「プロジェクターってこうやって使うんだ」というお客様からの声でした。
現在では、ひとつのガジェットとしてのプロジェクターの魅力はもちろんですが、「ユーザーのライフスタイルをより豊かにするようなものを作りたい」との気持ちを込めて製品づくりを行っています。
「MoGo 3 Pro」は日本では昨年9月に発売となりましたが、ベルリンで9月に開催された「IFA 2024」でもお披露目しました。これまでの展示では、「明るさ」「解像度」など性能にフォーカスすることが多かったのですが、今回は「寝室」「バスルーム」「子ども部屋」の3つの利用シーンを想定した展示へと大きく転換しました。

プロジェクターがさまざまなシーンで利用、体験できることにスポットを当てたのは、例えば、お風呂で映画を観る機会は年に数回あるかないかだと思いますが、さまざまな利用シーンに気づいていただくことで、プロジェクターという製品と人との距離をもっと縮めたいと考えたからです。
今後発売する製品も、ライフスタイルをより強く打ち出していく方向で進める方針です。設計、デザイン、色、そして、どのように伝えていくのかも非常に重要な要素です。現在、グローバル全体では6,100以上の店舗で展開しており、日本でも「Amazon.co.jp」「楽天市場」などのネットショップにとどまらず、オフラインのリアル店舗でも100店以上で展開しています。
―― 日本の家電量販店でも、人気が高まるモバイルプロジェクターを中心に売り場が拡充していく方向にはありますが、製品の魅力を伝える体験価値が十分に提供できているかというと、まだまだ発展途上というのが実情です。
Yang この点については日本だけではなく、欧米でも同じような試行錯誤の過程にあります。プロジェクターを雑誌やWEB、SNSなどで目にして興味を持ったお客様が実際に売り場へと足を運んでみると、投写されている映像が非常に小さかったり、展示スペースの制約により製品は展示のみで、実際の投写画面を確認できない場合もあります。課題は少なくありません。
ある店舗で12〜16インチ程度の大きさに投写された製品の展示を見たお客様から、「このプロジェクターはこんなに小さくしか投写できないのですか」と質問を受けたことがあります。プロジェクターの映像サイズは、設置距離によって変わり、距離を話すほど大きく投写できます。しかし、これは業界では一般的な知識でも、お客様にはあまり知られていないのだと気づきました。そのため、今後はどのようにわかりやすく伝えるかが課題だと感じています。
こうした啓発活動の必要性は、プロジェクター・メーカーに限らず、他の製品ジャンルにおいても多かれ少なかれ抱えている問題ではないでしょうか。我々はメーカーとしてユーザーの体験価値を高めるために、文字や動画、さらには限られた展示スペースでどのように製品の魅力をお伝えしていけばいいのか。日々努力している道筋の最中です。
現在、オーストラリアのメルボルンとシドニー、ニュージーランドのオークランドに直営店を展開しています。例えば、オーストラリア・メルボルンの店舗では約200平米の2階建ての建物で、1階が商品展示とカスタマーサポート、2階がオフィスになっています。オーストラリア市場では大型製品が多く、製品の魅力を訴える映画館のような空間を再現できる場所を必要としていました。

ひとつのブランドがプロジェクター専門の直営店を開設することは容易ではありませんが、幸運にも現地で信頼できるパートナーと巡り会うことができました。日本でも是非こうした機会が得られればと願っています。
デジタルコミュニケーションには限界がある。大切な“体験の場”
―― ホームプロジェクターのさらなる普及は一筋縄ではいかない大きなテーマで、メーカー、販売店、われわれメディア、業界が一丸となって取り組んでいかなければなりませんね。
Yang 今回の来日時、日本の税関で来日の目的を尋ねられ、「出張で来ました」とお答えしました。すると「どのような会社にお勤めですか」とさらに質問があり、「XGIMIというスマートプロジェクターのブランドに勤めています」とお伝えしました。すると、「XGIMIとAladdin X(アラジン エックス)はどのような関係にあるのか」と尋ねられました。税関の方が、Aladdin Xをご存じだったことに驚きました。
Aladdin Xの製品は体験価値をストレートにアビールしているため、多くの方に知っていただけるのだなと実感しました。我々もAladdin Xのように、長い時間をかけて説明をしなくても、どのような体験価値があるのかをわかっていただけるようにしたい。そのためには、デジタルでコミュニケーションを重ねてもそこにはやはり限界があり、体験をいただく場が重要となります。
雑誌やWEB、SNSで製品を知り、実際に体験できる店舗にまずは来ていただくこと。そこで、Aladdin Xのようにぱっと見て体験価値が想像できないものであっても、説明員がきちんと説明できる環境を整えていきたい。これは今すぐにとはいきませんが、中長期な視野で実現に向けて取り組んで参ります。また、国や地域により生活様式や文化も異なりますので、「製品のローカル化」もひとつの課題となります。
―― “ローカル化”という課題では、遊び心あふれた「MoGo 3 Pro」は各国での受け止め方や楽しみ方も異なってくるのではないでしょうか。
Yang 「MoGo 3 Pro」はキャンプシーンでの利用も想定した製品です。そのため、バッテリーは本体ではなくスタンドに備え、そこから給電する仕組みを採用しています。ところが発売後、日本市場ではポータブルプロジェクターに対し、バッテリーも搭載した“オールインワン”が求められていることがわかりました。

これはキャンプにおけるプロジェクターの位置づけに起因しています。欧米では100インチや120インチの大きなスクリーンで、音量も最大にして楽しみます。これに対して日本では、ルールを守り、周りにできるだけ迷惑をかけないよう気を配ります。
例えば、70インチクラスのポータブルスクリーンに対する反応を比べても、欧米では「すごくいいね」「車でどこかに行った時に使えるね」といった声が返ってきますが、日本では「どのように使えばいいのかすぐ思い浮かばないかもしれない」「外で使用したら迷惑がかかりそう」と大きく評価が異なります。
―― 審査会では同サイズの他のプロジェクターと比べると「明るさが取りやすい」「音量が出やすい」「音にノイズが少ない」といった点を評価する声も聞かれ、バッテリーを別としたことによるプラスの面も数多くありますね。
Yang なぜバッテリーを外したのかについては、非常に多くの要素を考慮して選択した結果です。その選択がご理解いただけたことを大変うれしく思います。今後は国や地域ごとの違いをさらに尊重していきたいと考えています。
ホームプロジェクターをもっともっと知ってもらいたい
―― 今回のVGP2025では、「HORIZON S Max」「HORIZON S Pro」が特別大賞を受賞しています。「MoGo 3 Pro」とはキャラクターが大きく異なる製品となります。
Yang 今回受賞した「HORIZON Sシリーズ」は、XGIMIが当初から手掛け、得意としている技術のイノベーションを強く意識をした製品となります。より完璧な製品を目指したプロフェッショナルなプロジェクターを、家庭用のプロジェクターとして使っていただくことを目指しました。欧米では「Hシリーズ」と称しており、“H”はホームを意味しています。

「Dolby Vision」「IMAX Enhanced」など最新技術に対応し、専門性の高いお客様のニーズにお応えしています。こうした製品を通じて、XGIMIプロジェクターの専門性を訴求すると同時に、XGIMIが作るポータブルプロジェクターの信頼性にもつなげて、一般のご家庭におけるXGIMI製品の認知拡大を目指します。
―― 審査会においてはとりわけ映像の明るさと色域の広さが高く評価されました。従来あまりできていなかった明るさと色域が両立されたことで、「リビングから寝室まで幅広い環境で使用できる」「アニメーションを見た時の鮮やかさが全然違う」といった声が聞かれ、“新しい価値を創造する製品”と言えると思います。
Yang 大変心強い言葉ですね。早速、製品担当者に伝えます。
―― ホームプロジェクター出荷量世界No.1を誇り、ワールドワイドのマーケットに精通する立場から、日本市場におけるスマートプロジェクターやホームシアターのさらなる普及を目指す上で何が必要なのか、ご提言をいただけますでしょうか。
Yang 中国と比べると、欧米や日本におけるプロジェクターの認知は立ち上がりが少し遅いペースです。しかし、先ほどの店頭課題のところでも述べましたが、まさにどこも同様のチャレンジが求められています。

ヨーロッパでは、日本で言うオーディオビジュアル(AV)をAudio Video Specialist(AVS)と表現します。「S」はスペシャリストの意味で、そのターゲット層は非常に限られています。専門性の高い人にアプローチする専門性の高い製品を、いかにマスにつなげ、マスマーケットにするか。そこにはブリッジが必要になると考えています。
大切なポイントのひとつはやはり、製品の設計やデザインではないでしょうか。2021 年にサムスンから登場したデスクライトのような円筒形の小型プロジェクター「The Freestyle」は、小型プロジェクターの概念を変え、これまでプロジェクターを知らなかった人に広めることに成功しました。
Aladdin Xの登場もまた、非常にアイコニックな出来事です。こうした製品は見るだけで、その性能や提供される体験が直感的に理解できます。特定の専門的な人々だけが手にするのではなく、マスマーケットに訴え、普及させていくことができる、イノベーションされた製品だと言えます。
ホームプロジェクターをさらに広く知ってもらいたい。そのためにXGIMIでは今、二つのチャレンジに取り組んでいます。ひとつめは、「XGIMI」というブランドをこれからどのように築き上げていくかというチャレンジ。そしてもうひとつは、プロジェクターというカテゴリーをどのように普及させていくかというチャレンジです。皆さんと思いは同じ。XGIMIのチャレンジにどうぞご期待ください。