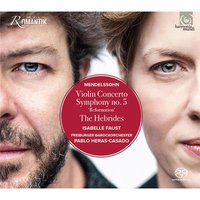�����o�ł�B&W�u802D4�v��������1�N�B�v������郊�t�@�����X�X�s�[�J�[�̖��͂Ƃ́H
�����o�ł̎������̃��t�@�����X�X�s�[�J�[�Ƃ��ē������ꂽB&W�u802D4�v�B��������1�N���o�߂��A�G�[�W���O���i���A���̐^�������悢�斾�炩�ɁB�����Ԃɂ킽��802D4�ƌ��������Ă����]�_�Ɛw�����̖��͂����B

�Ό��r�^�V�������ƂƂ��ɓ����B�T�C�Y�I�ɂ��ŗǂ̑I��
�Љ��ړ]�̂��ߖ{������������V����Ĉ�N�]��̌������o�����B�����͋��������h���C���������̂́A�ҏW�������̓w�͂̍b�゠���Č��݂ł͏����̂���f���ȉ��������������Ă���B�������̈ړ]�ɔ����ă��t�@�����X�E�X�s�[�J�[����V����AB&W�u802D4�v���V�K�������ꂽ�B

�����o�Ŏ������̖��̂́uWhite Room�i�z���C�g���[���j�v�B�ʐς͖�25�u�B�����͖�2.3m����ō���2.5m�ƂȂ��Ă���B�����z����F�P�[�u���͋ɑ��́uCV-S 5.5sq-3C�v���̗p����Ȃǖ{���Ȃ�ł͂̂�������������Ă���B1�N���o�߂��āA802 D4�ƂƂ��ɕ������̂̉����������X�ɐ����Ă���
802D4��B&W�ŏ㋉�́g800�V���[�Y�h�̏ォ��2�Ԗڂ̃��f���ł���B�g�b�v�ɌN�Ղ���u801D4�v�̓v���p���j�^�[�@�Ƃ������i�������A30��ȏ�̍L��ȃX�y�[�X�ł��Ȃ�����S���\�����邱�Ƃ͓���B��15��̖{���������Ŏg���̂�802D4�͍ŗǂ̑I���ł��낤�B
�{�@��3�E�F�C�A4�h���C�o�[���j�b�g�A�o�X���t�^�̃t���A�X�^���f�B���O���f���ł���B�E�[�t�@�[��200mm�G�A���t�H�C���E�R�[���~2�A�~�b�h�����W��150mm�R���e�B�j���A���E�R�[���A�g�D�C�[�^�[��25mm�_�C�������h�E�h�[���B800�V���[�Y�͏��ォ��e���j�b�g�ɓƗ������L���r�e�B��^���Ă������A�{�@�ł͋��U�r���̐v�v�z���Ɍ��܂ŃA�b�v�f�[�g������Ă���B
�E�[�t�@�[�̃G���N���[�W���[�̓t�����g�ƃT�C�h�o�b�t������̌^�̋��łȍ��Ŕ���≹�̉�܂͐����悤���Ȃ��B�~�b�h�͔�s���̂��v�킹�闬���`�̃G���N���[�W���[�Ƀ}�E���g����Ă���A����܂����U���������Ȃ��B
�g�D�C�[�^�[�͏����p�C�v�Ƀ}�E���g����Ă���̂ŗ��_��A�U���ȊO�̉��͏o�Ȃ��B�ȑO�̃��f���ł͏����p�C�v���t���L�V�u���Ɏ��t�����Ă������A�ŐV�̖{�@�ł͋ɂ߂ă��W�b�h�Ƀ}�E���g����Ă���B�o�X���t�_�N�g�͒�ʂɍI���Ƀ}�E���g����Ă���B
�����p�ɍœK�Ȃ����łȂ��������y�����Č��ł���
�v�v�z������M���m���悤�ɁA���̃X�s�[�J�[�͐U���̉��������Ȃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�Â���ɂ��̂悤�Ȃ��̂͂ǂ����ǂ��T���Ă��Ȃ��A�v���p���j�^�[�@�n���L�̌��i�����x�z�I���B������I�[�f�B�I�G���N�g���j�N�X�̓���������̂܂܂ɕ`���Ă����̂ŁA�u�����v�Ƃ����u���d���v�ɂ͂����Ă����B
�ł́u�I�[�f�B�I��v�Ƃ����u�y���݁v�ɂ͌����Ă��Ȃ��̂��Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ͑S���Ȃ��B�ڑ������I�[�f�B�I�@��̉��̓������悭������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ킿�I�[�i�[���]�ތX���̉������₷���Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B��{�I�ɂ͌������������A���Ƃ����B���e�[�W���������^��ǃA���v�Ȃ�Ô��œ����I�ȉ���������\���������B
�{���������ɏ풓����_���s���O�t�@�N�^�[���ɒ[�ɍ����A�L���t�F�[�Y�̃A���v�Ŗ炷�ƁA���̒��܂������t�@�����X�炵���^�ʖڂŐ܂�ڐ������A����ł��Ē����Ԃ̎����ɑς�����O���̗��Ȃ��T�E���h��������B���F�n�̉����������[���b�p���̃A���v�Ȃ炳��Ɍ������T�E���h�����o���邾�낤�B���b�N�X�}����}�b�L���g�b�V���̂悤�ȓ`�����郁�[�J�[�̃A���v���ƃ~���[�W�J���e�B�̍����\�������҂ł���B
�ǂ�ȃW�����������^�ʖڂɉ��y�̃��A���Y����\������
�㋉�@��801�n���N���V�b�N��僌�[�x���̃X�^�W�I�ł��g���Ă��邱�Ƃ���AB&W�̓N���V�b�N�����ƔF�����Ă�����ǎ҂������邱�Ƃ��낤�B�������Ȃ���A����͊Ԉ���Ă���Ɛ\���グ����Ȃ��B
�Ƃ����̂��v���̌���Ƃ������̂́A���Ƃ������W���������N���V�b�N�ł��A�A�}�`���A�Ƃ͎����̈قȂ�剹�ʂō�Ƃ�i�߂���̂ŁAB&W�̐��i�̓p���N���b�N�ɑ�\����錃�������y�̐M�������Ă��r�N�Ƃ����Ȃ��̂��B
�������A�ǂ�ȃW�������ł����^�ʖڂɕ\�����邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂����A���y�����A���Y�����ɒ������Ƃ���s�ׂ̓I�[�f�B�I�̐�������@�̈���ƕM�҂͊m�M����B���̃X�s�[�J�[�̗ǂ�����葽���̈��D�Ƃɒm���Ă������������B
�p�c��Y�^�n�C���]����ƂƂ��ɐi���𑱂����X�s�[�J�[

����Ȏ��A�t�B���b�v�X�E�N���V�b�N�X���L���r�l�b�g�̖����A�t���[���ɐU������z�u�����v���p�̐Ód�^�X�s�[�J�[���g���Ă��邱�Ƃ�m�����B��������ۂɎ�������Ɖ��̗����オ�肪��������Ȃ����肩�A�c�ݗ���1���ȉ��ŁA�N�x�̍����A���X���������������B�܂��Ɏ��R�ȉ��ł������B
�����Ė�20�N���̃X�s�[�J�[���g�������A�n�C���]���オ�������A24bit�̃_�C�i�~�b�N�����W���Đ����邱�Ƃ�����ɂȂ�A���������̍Đ��ɂ��Ή��ł��Ȃ��Ȃ����B���N�̖��@�ł����������Ɏc�O�Ɏv�����B
���̊Ԃɂ�B&W�̃X�^�W�I���j�^�[�͒����Ȑi���𐋂��Ă������B���̗����オ��̋��������Ȃ��A�L���r�l�b�g�̐U�����ɏ��ŁA�c�ݗ���1���ȉ��ɓ��B���Ă����BA/D�AD/A�R���o�[�^�[�ȂǍĐ��@��̉����ɂ߂ăX�g���[�g�ɍĐ����Ă����B�����Ƀ_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�̐i���������邱�Ƃ��ł����̂��B
�������Ȃ���AB&W�̃A�C�R���ł���~�b�h�����W�̃C�G���[�E�P�u���[�U���ɂ͌������������߁A���炭�͐V���i�̓o������҂��Ă����B
�M���ł���p�[�g�i�[�Ƃ���802D3������ɓ�������
�₪��B&W����V����800�V���[�Y�����������ƃA�i�E���X���������BD3�V���[�Y�ł���B�t���A�^�Ƃ��ẮAB��W 802D3����s��������A�������邱�Ƃ������A���̉��Ɋ��������B
�_�C�A�����h�E�g�D�C�[�^�[�ƃR���e�B�j���A���E�~�b�h�����W�Ƃ̉��̌q���肪���|�I�Ɍ��サ���B�܂��A�e�U���̔w��̉������œK�ɏ�������@�\���̗p���邱�ƂŁA�Đ����u�̉������܂łɑ̌��ł��Ȃ������قǁA�F�t���Ȃ��X�g���[�g�ɍĐ����邱�Ƃ��ł����B���͂�������邱�Ƃ����߁A���y���y���ނɂ���A�d���Ɍ����������ɂ���A�M���ł���p�[�g�i�[�ƂȂ����B
�����āAD3�����A����ɐi���𐋂���B��W 802D4�͂���ɏ��ʂ̑��������Đ����A���̌q������܂��܂����サ���B���y�̃f�B�e�[�����ɂ߂ďڍׂɍĐ��������X�s�[�J�[�ł���B
�I�����_�̃y���^�g�[���́AB&W���j�^�[���g�p���Ă��郌�[�x���ł��邪�A���X�̃N���V�b�N�E�A���o���͎���ł��A���Ԍo�߂ƂƂ��ɐ������ꂽ�{���̎������ł��R���T�[�g���Ȃ���̗Տꊴ�Œ������Ƃ��ł���B���̍Đ��͂̍����͒��N�̋Z�p�ɗ��ł����ꂽ���ʂ��Ǝ������Ă���B
�����R�v�^�W���@�A802D4�̑I���͐^�ɑÓ��Ȃ��̂ƌ����Ă悢

�����o�ł̐V���������v�H����1�N���o�߂��A�����\���������������Ă��������B�����̃��t�@�����X�X�s�[�J�[B&W 802D4���G�[�W���O���i�B�����Ō��݂̃p�t�H�[�}���X���܂߂��A����1�N���܂�̎������̕ω��i�[���j��U��Ԃ��Ă݂����B
�Ƃ���ŁA���t�@�����X�Ƃ͉����B����͊�ł���B�X�s�[�J�[�͉��y�ӏܗp�̃v���_�N�c�����A���̗p�r�ł͌����p�̖�ڂ�����A���j�^�[�X�s�[�J�[�Ƃ��Đ��E���̃X�^�W�I�ʼnғ�����A�W���@�Ƃ�������802D4�̑I���́A�^�ɑÓ��Ȃ��̂ƌ����Ă悢�B
�Ⴆ�ΐ��E�I�ɒm����A�r�[���[�h�E�X�^�W�I�ł́AB&W 800D4�V���[�Y�����t�@�����X�Ƃ���Ă���B�܂�A���̗ǂ������f���邽�߂̓���Ƃ��Ďg���Ă���킯���B����ƌ����Ă��܂��̂̓X�s�[�J�[�ɂ͋C�̓ł�������Ȃ����A����V�X�e����B&W���g���Ă���l�ɂ��\����Ȃ����A���̏ꍇ�͎��n�D�i�Ƃ��Ă̑ΏۂƖړI���قȂ�B
�����v���ɁAB&W�i����800D4�V���[�Y�j�́A�v�������f���铹��Ƃ��Ă��A��̉��y�ӏܗp�ɂ��A������̎g�����ɂ����Ă��|�e���V�������\�ɔ������郔�@�[�T�^�C���ȃX�s�[�J�[�ł���B
�����{���̎����e�X�g�Ŏg���P�[�X�ł��A�Ⴆ�A���v�̓������I�݂ɖ炵�����傢�Ɋ��S�������邱�Ƃ�����A���y�\�[�X�̎������������o�������ƂŁA�e�X�g��Y��Ă������R�Ɖ��y�ɒ��������Ă��܂����Ƃ�����B���������X�s�[�J�[�́A���s������n���Ă����������Ȃ��B
���j�^�[�X�s�[�J�[�ɂ̓��j�^�[�X�s�[�J�[�Ȃ�̌��R�Ƃ����X�^�C�������邪�A�����͉��X�ɂ��Ė����ȃf�U�C���������BB��W�ɂ͂���ȕ���͔��o���Ȃ��B���f���`�F���W���o�邲�Ƃɂǂ�ǂ�������Ȃ��Ă����B�ŏ��͈�a���̂������m�[�`���X�`���[�u�́A���́h�`�����}�Q�h���A���ł͂�������ɂ����i!?�j�B
�ł������ȃG�[�W���O���ʂ͒��̐U�镑���ƍ���̔���
�܂��ŐV��805D4 Signature�̂��̃~�b�h�i�C�g�E�u���[�A�N�₩�ȍ��ɂ̋P���̌p�ڂ̂Ȃ����E���h�G���N���[�W���[�́A���ꍛ�ꂷ��悤�Ȕ������t�B�j�b�V�����B�����Ɏ��܂���2�̃h���C�o�[�̓V�[�����X�ɂȂ���A�s���|�C���g�Œ�ʂ����܂�B�{���̓��W�ł��劈�Ă��ꂽ���@�́A�@��̉����̈Ⴂ���I�݂ɏs�ʂ��Ă��ꂽ�B����ł́A���H�[�J���̐��X�����⃔�@�C�I�����̉��₩�������ɖ��f�I�ɒ������Ă���������B

�V�i�̃X�s�[�J�[�́A�������u���Ă����ɂ������Ŗ���̂ł͂Ȃ��B�����A�u�G�[�W���O�v�Ƃ����炵���݂��K�v���B
��������802D4����1�N�̃G�[�W���O�ƁA�������̑��엎�������ŏ��X�ɕω����Ă����킯�����A�ł������Ȃ̒��̐U�镑���ł���B�ŏ��̓_�u�t���C���ł������ቹ���A�g���x�Ɉ������܂��Ă����B�����t�щ��������Ă����R���g���o�X�̃s�b�`����荎���ɒ�������悤�ɂȂ��Ă����̂��B
����Ń_�C�������h�E�g�D�C�[�^�[�̍���̔������A���̂Ƃ����i�ƐL�т₩�ɂȂ��Ă���B���H�[�J���̗]�C�̏������킪�i�`�������ȃA���r�G���g�Ƌ��ɔ�������������̂��B
��ʉƒ�ł���A�����ƈ�J���Ɏ~�܂��ăG�[�W���O���i�߂��邪�A�������Ƃ������i��A�@�ނ̕p�ɂȏo��������̂ŁA��������炵���ނ̂�����B����ł������܂Ńp�t�H�[�}���X���[�������̂́A��X�]�_�Ƃ͂������A�ҏW�������厖�Ɉ��łĂ��������ł���B
�����ɏo�����̂��y�����Ȃ��Ă����B���ꂪ���̋ߋ��ł���B
�i�F������Ѓf�B�[�A���h�G���z�[���f�B���O�X�j
�{�L���́w�G���E�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[197���x����̓]�ڂł�