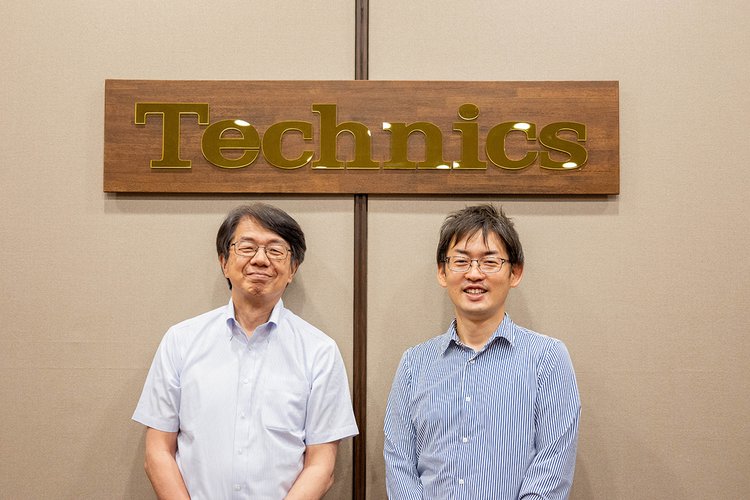“光ディスク”再生技術の発展に貢献
日本のオーディオ/ビジュアルの最先端を切り拓いて30年。テクニクス復活の立役者・井谷哲也氏ロングインタビュー
新生テクニクスのCTOとして、ブランドの「顔」を担ってきた井谷哲也氏。同氏のキャリアは、まさに日本の“光ディスクメディア”の発展と密接に関わっている。入社してすぐにテクニクスのCDプレーヤー初号機の設計に携わったのち、レーザーディスク・DVD・Blu-rayとパナソニックの「円盤」再生技術を開拓してきた。2021年には、イギリスのWhat Hi-Fiマガジンで「Outstanding Contribution」として表彰されるなど、世界的にもその名を知られている。この春にCTOを退任したことから、改めて井谷氏のこの30年の仕事を振り返るロングインタビューを実施。新CTO奥田忠義氏にも登場いただき、引き継がれるテクニクスブランドの「思い」を聞いた。
テクニクスは1965年の創設以来、革新的技術を武器に数々の銘機を世に送り出してきた名門ブランドである。ホームオーディオを取り巻く環境変化の波にもまれて2010年には休止に追い込まれ、世界中のオーディオファンが悲嘆に暮れたが、その4年後に劇的な復活を果たし、いまはかつてのように充実した製品群を揃えて高評価を獲得。ハイファイオーディオの重要な一角を占めるブランドに返り咲いた。
テクニクスの歴史をたどるときに必ず名前が上がる人物の一人が、銘機を生んだエンジニアでブランド復活時にも重要な役割を演じた井谷哲也氏である。ごく最近までCTO(Chief Technical Officer)をつとめ、チーフエンジニアとして設計を牽引してきたキーパーソンに大阪・門真のテクニクス試聴室でお話をうかがった。
井谷氏は1980年に松下電器産業(現パナソニック)に入社。志望通りステレオ事業部の設計部門に配属され、テクニクス製品の設計に携わることになった。上司は当時の技術部長で後に音響研究所所長に就任する小幡修一氏。ダイレクトドライブ方式のターンテーブルを導入した立役者だ。ちなみに2014年に井谷氏と二人三脚でテクニクス復活プロジェクトを進めた小川理子氏は井谷氏の6年後に入社し、所長就任後の小幡氏のもとでテクニクスの次世代を担う研究に携わっていた。若干の時差があるとはいえ、約30年後にブランド復活プロジェクトをともに担うことになった井谷氏と小川氏が共通の上司のもとで仕事をしていたのは興味深いエピソードだ。
入社の翌年、井谷氏はCDプレーヤーの開発プロジェクトに配属された。デジタルオーディオは当時まだ未知の領域で、事業部内にCDプレーヤーの経験を持つエンジニアはいなかった。そんななか、いきなり第一号機のソフトウェア開発を任されたのだ。
「当時のステレオ事業部は人気が高く、同期から十数人が配属されましたが、そのなかの4人が翌年発売予定のCDプレーヤーの開発に振り分けられました。一年間の研修を終えたばかりで、何もわからない新人です。しかもCDプレーヤーはまだ世界中どこにも存在していない。翌年の発売まで、かなりきつかったけど、なんとか乗り切ることができました。でも、いまから思うと恵まれていましたね。いきなりゼロからやってもなんとかなるという自信がつきましたから」。苦労の末に完成したCDプレーヤー第一号機のSL-P10は縦型のメカドライブを採用。1982年秋に登場した各社の第一号機は、ソニーを除き、ほぼ全社がこの縦型スタイルを採用していた。
CDの誕生は大きな話題を呼んだが、当時はまだレコードが主流で、本格的な普及には数年を要した。突破口となった各社の低価格モデルのなかでも、ひときわ目を引いたのがテクニクスのSL-XP7(1985年発売)だ。
「第一号機のSL-P10では信号処理回路や光学サーボ等、13個の半導体を開発しましたが、SL-XP7ではそれを合理化して一気に小型化しました。とはいえ当時は線幅4μmの設計ルールです。いまの最先端プロセスは4nmですから、ちょうど千分の1ですね。その差は面積で効いてきますから、1000×1000で100万分の1、隔世の感があります」。ちなみにSL-XP7のデザインは、ジャケットサイズのレコードプレーヤー「SL-10」へのオマージュ。レコードからCDへの橋渡しを象徴する製品の一つといえそうだ。
CDプレーヤーの小型化はクルマやラジカセなど用途の拡大を促し、低価格化も追い風となって普及が一気に加速する。1986年にはレコードプレーヤーとCDプレーヤーの売上が逆転し、本格的なCD時代に突入した。その頃ほとんどのオーディオメーカーがターンテーブルなどアナログ機器の開発から撤退し、カートリッジの設計者がレーザーピックアップの開発に取り組むなど、社内体制にも変化の波が押し寄せる。
そんなとき、井谷氏は自ら希望してCDプレーヤーからレーザーディスクプレーヤーの開発部隊に移ることになった。オーディオから映像、そしてテクニクスからパナソニックへの大胆な転身である。CDが普及期に入った途端、なぜ異動を希望したのだろう。
「自分から他の仕事への異動を希望したのはこのときだけです。そのままCDの開発を続けても、技術者としてあまり成長しないのではと思ったんですね。それで、当時の上司だった四角利和さんのところにレーザーディスクをやらせてほしいと、直談判に行きました。CDプレーヤーの開発はむちゃくちゃしんどかったけど、日々成長している実感があったんです。その体験が染み付いていたので、ルーティン化すると面白くないなと(笑)。要するにクソ生意気だったんですよ(笑)。でも、四角さんは私の願いを聞いてくれて、その後レーザーディスク・DVDと、直属の上司・部下の関係でご指導頂きました」
もともとオーディオが好きで高校時代にはアンプやスピーカーの製作も手がけていたという井谷氏。オーディオメーカーへの就職も考えたが、大学の研究室の教授から「オーディオは過当競争になってるから、そこだけにこだわらない方ががいい。松下電器は映像にも強い」とアドバイスを受け、試験を受けることを決めたという。このアドバイスが、その後井谷氏が築くキャリアにも影響を及ぼすことになる。
あえて新しいテーマに挑戦する姿勢は、最初は自ら望んで選んだ道だった。しかし、その後は周囲から請われる形でほぼ10年単位で異動が続く。CDプレーヤーの完成から2014年のブランド復活にいたるまでの約30年間は、CD、LD、DVD、Blu-rayと四世代に及ぶ光ディスクの進化過程にピタリと重なる。その進化を牽引する役割を担ってきたことが、やがてテクニクス復活を支える原動力になったのだ。その意味はあとで説明するとして、まずは光ディスクの発展に井谷氏がどう関わってきたのか、簡単に振り返ってみよう。
CD誕生の前年に発売されたレーザーディスク(LD)は高速回転する直径30cmのディスクを光学ピックアップで読み取る非接触方式のビデオディスクで、1981年に登場したあと、DVDが普及し始める1990年代後半までパイオニア、ヤマハ、ソニーなど多くのメーカーがプレーヤーを発売していた。
パナソニックのフラグシップモデル(LX-1000、1990年発売)は、デジタルTBC(タイムベースコレクタ)を世界で初めて採用して映像信号のジッターを低減したり、輝度信号と色信号を分離するフィルターをデジタルで構成するなど、デジタル技術を積極的に導入して画質改善に取り組んだことが当時高く評価された。
LDの映像信号はDVDとは異なりアナログ方式なのだが、パナソニックは映像信号処理にデジタル技術を導入することで歪やノイズを効果的に改善できることを実証した。「映像信号をデジタルで処理できるようになったのは、半導体の進化が背景にありました。世界初のデジタル映像信号処理用LSIの開発に着手したのが、1988年です」と井谷氏は当時を振り返る。同技術は業界で高く評価され、パナソニックが同業他社にLSIを供給する例もあったという。
LDはサイズや使い勝手が要因で普及が頭打ちになり、ビデオディスクの主役はDVDに置き換わっていく。パナソニックは1998年に発売したフラグシップの「DVD-H1000」でプログレッシブ変換という世界初のブレークスルーを成し遂げ、高画質再生の新たな潮流を作り出した。DVDの規格策定を担う企業の一つとして重要な役割を担っていたことがLD時代との大きな違いで、東芝やタイム・ワーナーと組んでソニー・フィリップス陣営との規格競争を克服しつつ、技術面でも新たな挑戦を仕掛ける必要があった。そこで井谷氏に白羽の矢が立つ。
「LDが終息に向かうなか、社内である種の失業状態だったときに『DVDでなにか画期的なことを考えろ』という指示が、当時事業部長をされていた四角さんから下りました。そこで思いついたのがプログレッシブ変換です。そのときはLSIを自分たちで設計する時間がなくカナダのデバイスメーカーと組みましたが、LSIに目処がたったあとの製品設計も任されることなりました」。
映画フィルムの映像情報をそのまま出力するプログレッシブ処理は、インターレース方式のようにディテール描写が劣化することがなく、画面のちらつきを抑える効果も大きい。高級オーディオ機器を思わせる堅固な筐体設計も功を奏し、DVD-H1000(1998年発売)と後継機のDVD-H2000(2001年発売)は画質と音質の両方でDVD時代を牽引する存在となった。
DVD-H1000が発表された直後、画質検証記事を担当した私は井谷氏にインタビューを行った記憶がある。「専門誌の取材を受けたのは初めてのことでよく憶えています」と、当時の誌面を見ながら、今回の取材でもプログレッシブの話題でしばし盛り上がった。井谷氏と私は同い年なので二人とも当時40歳。その後、25年を超える長いお付き合いになるとは想像もしていなかった。
21世紀に入ると、さらなる大容量化を目指して次世代DVDの規格化が動き出す。パナソニックはハリウッドの映画産業とのつながりを活かしながらソニーとともにBlu-ray陣営の中核で準備を進めていった。井谷氏は2005年にBlu-rayのプロジェクトに異動し、プレーヤー導入時に技術面で重要な役割を演じる。特に、今日のDIGAシリーズの基盤となるクロマアップサンプリングなどの基幹技術を提唱し、具体化する作業を進めたことに重要な意味がある。
「ハリウッドのサポートを得ることがフォーマット競争のカギを握っていたので、パナソニックでは現地に研究所(パナソニック・ハリウッド研究所)を設立し、そこが中心となってロビー活動や技術の検討をしていました。そこで開発したMPEG4がベースになってBlu-rayが生まれたんです。その後、BD-ROM再生1号機を開発した直後に、ハリウッド研究所のメンバーが画質に疑義を呈してきたことがありました。原画と比べると納得できない部分があるというんです。それで私が現地に飛び、一週間議論するなかで発見したのがクロマアップサンプリングのアルゴリズムでした」。
輝度信号に対して色信号の情報量は4分の1にとどまり、アップサンプリングのやり方で画質が大きく変わる。そこに投入したパナソニックの手法はDIGAシリーズの高画質を支えるバックボーンとなり、いまもアドバンテージを確保している。他の信号処理技術も含めて統合した「ユニフィエ(UniPhier)」プラットフォームが完成したのもこの頃のことだ。
光ディスクの進化を支えてきた井谷氏のキャリアは1980年代前半のCDプレーヤー開発に原点がある。いったん終息したテクニクスブランドを復活させる話が2013年に持ち上がったとき、井谷氏に白羽の矢が立ったのは、そこに直接の理由があると考えるのが普通だろう。だが、それに加えてDVDからBDにいたるデジタルコンポーネントのソフトウェア開発、企画から設計までカバーできる幅広く柔軟なスキル、海外を含むメディアとのパイプの太さなど、これまで培ってきた経験の成果が評価されたのではないか。
井谷氏本人はこう分析する。「DIGAは単独では画も音も出ないコンポーネント形式で、そこにオーディオとの共通点があります。アンプやスピーカーがなければプレーヤーだけでは音が出ませんよね。それからもう一つ、DVDなどオーディオとは別のことをやっていたおかげで、環境の変化に流されず、オーディオにもう一度戻ってこれたのかもしれません。ガラパゴスで生き残っていたゾウガメだと思ってます(笑)」。
ブランド復活の経緯はPHILE WEBでも何度か紹介してきた通りで、まずは井谷氏が2013年に復活プロジェクトのリーダーに就任。2014年から参加する小川理子氏とともに新世代テクニクス製品の開発を強力に推し進めてきた。今回のインタビューでは、社内で復活プロジェクトが決まる直前にもいくつか動きがあったことが明かされた。
「DIGA担当だった2010年にビデオとオーディオのビジネスユニットが統合されて、私がオーディオも見るようになりました。まだテクニクス復活という話ではなくて、ホームシアターやサウンドバーが中心でしたが、そんなときに後のJENOエンジンの母体となるものをマイクロコンポ(SC-PMX5)に導入したり、PMX5のハイレゾ対応に取り組むなど、ピュアオーディオの動きが実を結び始めます。PMX5を国内外の評論家に聴いてもらったところ、『この音ならいっそのことテクニクスブランドにしたらどうか』と言われたことも動機付けになりました」。
井谷氏は2023年4月にCTOからテクニカル・エキスパートの立場に変わったが、今後も引き続きテクニクス事業をサポートしていくという。一方、井谷氏と10年にわたって製品開発に取り組んできた奥田忠義氏が新たにCTOに就任。JENOエンジンの開発を進めていた奥田氏は「CTOは業界の流れや技術の流れを見据えていく役割も担いますが、それだけでなく先行技術と要素技術開発の責任者も兼ねています。これからは若い音楽ファンにもテクニクスの魅力を届けていきたいと考えています」と抱負を語る。
CTOの仕事を奥田氏に委ねることで井谷氏には時間の余裕ができたのだろうか。テクニクスでやりたいことがまだたくさんあるという。「いまのオーディオは、デジタル信号処理技術が急速な進歩を遂げています。従来のアプローチではできないことがまだたくさんあって、アンプもレコードプレーヤーも『宝の山』に見えます(笑)。特にレコードは音溝に刻まれている『真実』がなにか、誰もわからない神秘性がありますよね。追求するとどんどん情報が出てくる面白さ。それがある限り、オーディオがすたれることはありません」。
入社後すぐに、CDプレーヤー初号機のソフトウェア開発を任される
テクニクスは1965年の創設以来、革新的技術を武器に数々の銘機を世に送り出してきた名門ブランドである。ホームオーディオを取り巻く環境変化の波にもまれて2010年には休止に追い込まれ、世界中のオーディオファンが悲嘆に暮れたが、その4年後に劇的な復活を果たし、いまはかつてのように充実した製品群を揃えて高評価を獲得。ハイファイオーディオの重要な一角を占めるブランドに返り咲いた。
テクニクスの歴史をたどるときに必ず名前が上がる人物の一人が、銘機を生んだエンジニアでブランド復活時にも重要な役割を演じた井谷哲也氏である。ごく最近までCTO(Chief Technical Officer)をつとめ、チーフエンジニアとして設計を牽引してきたキーパーソンに大阪・門真のテクニクス試聴室でお話をうかがった。
井谷氏は1980年に松下電器産業(現パナソニック)に入社。志望通りステレオ事業部の設計部門に配属され、テクニクス製品の設計に携わることになった。上司は当時の技術部長で後に音響研究所所長に就任する小幡修一氏。ダイレクトドライブ方式のターンテーブルを導入した立役者だ。ちなみに2014年に井谷氏と二人三脚でテクニクス復活プロジェクトを進めた小川理子氏は井谷氏の6年後に入社し、所長就任後の小幡氏のもとでテクニクスの次世代を担う研究に携わっていた。若干の時差があるとはいえ、約30年後にブランド復活プロジェクトをともに担うことになった井谷氏と小川氏が共通の上司のもとで仕事をしていたのは興味深いエピソードだ。
入社の翌年、井谷氏はCDプレーヤーの開発プロジェクトに配属された。デジタルオーディオは当時まだ未知の領域で、事業部内にCDプレーヤーの経験を持つエンジニアはいなかった。そんななか、いきなり第一号機のソフトウェア開発を任されたのだ。
「当時のステレオ事業部は人気が高く、同期から十数人が配属されましたが、そのなかの4人が翌年発売予定のCDプレーヤーの開発に振り分けられました。一年間の研修を終えたばかりで、何もわからない新人です。しかもCDプレーヤーはまだ世界中どこにも存在していない。翌年の発売まで、かなりきつかったけど、なんとか乗り切ることができました。でも、いまから思うと恵まれていましたね。いきなりゼロからやってもなんとかなるという自信がつきましたから」。苦労の末に完成したCDプレーヤー第一号機のSL-P10は縦型のメカドライブを採用。1982年秋に登場した各社の第一号機は、ソニーを除き、ほぼ全社がこの縦型スタイルを採用していた。
オーディオからビジュアルへ。LDプレーヤーの開発チームに参加
CDの誕生は大きな話題を呼んだが、当時はまだレコードが主流で、本格的な普及には数年を要した。突破口となった各社の低価格モデルのなかでも、ひときわ目を引いたのがテクニクスのSL-XP7(1985年発売)だ。
「第一号機のSL-P10では信号処理回路や光学サーボ等、13個の半導体を開発しましたが、SL-XP7ではそれを合理化して一気に小型化しました。とはいえ当時は線幅4μmの設計ルールです。いまの最先端プロセスは4nmですから、ちょうど千分の1ですね。その差は面積で効いてきますから、1000×1000で100万分の1、隔世の感があります」。ちなみにSL-XP7のデザインは、ジャケットサイズのレコードプレーヤー「SL-10」へのオマージュ。レコードからCDへの橋渡しを象徴する製品の一つといえそうだ。
CDプレーヤーの小型化はクルマやラジカセなど用途の拡大を促し、低価格化も追い風となって普及が一気に加速する。1986年にはレコードプレーヤーとCDプレーヤーの売上が逆転し、本格的なCD時代に突入した。その頃ほとんどのオーディオメーカーがターンテーブルなどアナログ機器の開発から撤退し、カートリッジの設計者がレーザーピックアップの開発に取り組むなど、社内体制にも変化の波が押し寄せる。
そんなとき、井谷氏は自ら希望してCDプレーヤーからレーザーディスクプレーヤーの開発部隊に移ることになった。オーディオから映像、そしてテクニクスからパナソニックへの大胆な転身である。CDが普及期に入った途端、なぜ異動を希望したのだろう。
「自分から他の仕事への異動を希望したのはこのときだけです。そのままCDの開発を続けても、技術者としてあまり成長しないのではと思ったんですね。それで、当時の上司だった四角利和さんのところにレーザーディスクをやらせてほしいと、直談判に行きました。CDプレーヤーの開発はむちゃくちゃしんどかったけど、日々成長している実感があったんです。その体験が染み付いていたので、ルーティン化すると面白くないなと(笑)。要するにクソ生意気だったんですよ(笑)。でも、四角さんは私の願いを聞いてくれて、その後レーザーディスク・DVDと、直属の上司・部下の関係でご指導頂きました」
もともとオーディオが好きで高校時代にはアンプやスピーカーの製作も手がけていたという井谷氏。オーディオメーカーへの就職も考えたが、大学の研究室の教授から「オーディオは過当競争になってるから、そこだけにこだわらない方ががいい。松下電器は映像にも強い」とアドバイスを受け、試験を受けることを決めたという。このアドバイスが、その後井谷氏が築くキャリアにも影響を及ぼすことになる。
LD、DVD、Blu-rayと光ディスクの進化を牽引し続ける
あえて新しいテーマに挑戦する姿勢は、最初は自ら望んで選んだ道だった。しかし、その後は周囲から請われる形でほぼ10年単位で異動が続く。CDプレーヤーの完成から2014年のブランド復活にいたるまでの約30年間は、CD、LD、DVD、Blu-rayと四世代に及ぶ光ディスクの進化過程にピタリと重なる。その進化を牽引する役割を担ってきたことが、やがてテクニクス復活を支える原動力になったのだ。その意味はあとで説明するとして、まずは光ディスクの発展に井谷氏がどう関わってきたのか、簡単に振り返ってみよう。
CD誕生の前年に発売されたレーザーディスク(LD)は高速回転する直径30cmのディスクを光学ピックアップで読み取る非接触方式のビデオディスクで、1981年に登場したあと、DVDが普及し始める1990年代後半までパイオニア、ヤマハ、ソニーなど多くのメーカーがプレーヤーを発売していた。
パナソニックのフラグシップモデル(LX-1000、1990年発売)は、デジタルTBC(タイムベースコレクタ)を世界で初めて採用して映像信号のジッターを低減したり、輝度信号と色信号を分離するフィルターをデジタルで構成するなど、デジタル技術を積極的に導入して画質改善に取り組んだことが当時高く評価された。
LDの映像信号はDVDとは異なりアナログ方式なのだが、パナソニックは映像信号処理にデジタル技術を導入することで歪やノイズを効果的に改善できることを実証した。「映像信号をデジタルで処理できるようになったのは、半導体の進化が背景にありました。世界初のデジタル映像信号処理用LSIの開発に着手したのが、1988年です」と井谷氏は当時を振り返る。同技術は業界で高く評価され、パナソニックが同業他社にLSIを供給する例もあったという。
LDはサイズや使い勝手が要因で普及が頭打ちになり、ビデオディスクの主役はDVDに置き換わっていく。パナソニックは1998年に発売したフラグシップの「DVD-H1000」でプログレッシブ変換という世界初のブレークスルーを成し遂げ、高画質再生の新たな潮流を作り出した。DVDの規格策定を担う企業の一つとして重要な役割を担っていたことがLD時代との大きな違いで、東芝やタイム・ワーナーと組んでソニー・フィリップス陣営との規格競争を克服しつつ、技術面でも新たな挑戦を仕掛ける必要があった。そこで井谷氏に白羽の矢が立つ。
「LDが終息に向かうなか、社内である種の失業状態だったときに『DVDでなにか画期的なことを考えろ』という指示が、当時事業部長をされていた四角さんから下りました。そこで思いついたのがプログレッシブ変換です。そのときはLSIを自分たちで設計する時間がなくカナダのデバイスメーカーと組みましたが、LSIに目処がたったあとの製品設計も任されることなりました」。
映画フィルムの映像情報をそのまま出力するプログレッシブ処理は、インターレース方式のようにディテール描写が劣化することがなく、画面のちらつきを抑える効果も大きい。高級オーディオ機器を思わせる堅固な筐体設計も功を奏し、DVD-H1000(1998年発売)と後継機のDVD-H2000(2001年発売)は画質と音質の両方でDVD時代を牽引する存在となった。
ハリウッドとのつながりを活かし、次世代規格Blu-rayの開発に着手
DVD-H1000が発表された直後、画質検証記事を担当した私は井谷氏にインタビューを行った記憶がある。「専門誌の取材を受けたのは初めてのことでよく憶えています」と、当時の誌面を見ながら、今回の取材でもプログレッシブの話題でしばし盛り上がった。井谷氏と私は同い年なので二人とも当時40歳。その後、25年を超える長いお付き合いになるとは想像もしていなかった。
21世紀に入ると、さらなる大容量化を目指して次世代DVDの規格化が動き出す。パナソニックはハリウッドの映画産業とのつながりを活かしながらソニーとともにBlu-ray陣営の中核で準備を進めていった。井谷氏は2005年にBlu-rayのプロジェクトに異動し、プレーヤー導入時に技術面で重要な役割を演じる。特に、今日のDIGAシリーズの基盤となるクロマアップサンプリングなどの基幹技術を提唱し、具体化する作業を進めたことに重要な意味がある。
「ハリウッドのサポートを得ることがフォーマット競争のカギを握っていたので、パナソニックでは現地に研究所(パナソニック・ハリウッド研究所)を設立し、そこが中心となってロビー活動や技術の検討をしていました。そこで開発したMPEG4がベースになってBlu-rayが生まれたんです。その後、BD-ROM再生1号機を開発した直後に、ハリウッド研究所のメンバーが画質に疑義を呈してきたことがありました。原画と比べると納得できない部分があるというんです。それで私が現地に飛び、一週間議論するなかで発見したのがクロマアップサンプリングのアルゴリズムでした」。
輝度信号に対して色信号の情報量は4分の1にとどまり、アップサンプリングのやり方で画質が大きく変わる。そこに投入したパナソニックの手法はDIGAシリーズの高画質を支えるバックボーンとなり、いまもアドバンテージを確保している。他の信号処理技術も含めて統合した「ユニフィエ(UniPhier)」プラットフォームが完成したのもこの頃のことだ。
光ディスクの進化を支えてきた井谷氏のキャリアは1980年代前半のCDプレーヤー開発に原点がある。いったん終息したテクニクスブランドを復活させる話が2013年に持ち上がったとき、井谷氏に白羽の矢が立ったのは、そこに直接の理由があると考えるのが普通だろう。だが、それに加えてDVDからBDにいたるデジタルコンポーネントのソフトウェア開発、企画から設計までカバーできる幅広く柔軟なスキル、海外を含むメディアとのパイプの太さなど、これまで培ってきた経験の成果が評価されたのではないか。
井谷氏本人はこう分析する。「DIGAは単独では画も音も出ないコンポーネント形式で、そこにオーディオとの共通点があります。アンプやスピーカーがなければプレーヤーだけでは音が出ませんよね。それからもう一つ、DVDなどオーディオとは別のことをやっていたおかげで、環境の変化に流されず、オーディオにもう一度戻ってこれたのかもしれません。ガラパゴスで生き残っていたゾウガメだと思ってます(笑)」。
高級オーディオブランドに再び還る。テクニクス復活に尽力
ブランド復活の経緯はPHILE WEBでも何度か紹介してきた通りで、まずは井谷氏が2013年に復活プロジェクトのリーダーに就任。2014年から参加する小川理子氏とともに新世代テクニクス製品の開発を強力に推し進めてきた。今回のインタビューでは、社内で復活プロジェクトが決まる直前にもいくつか動きがあったことが明かされた。
「DIGA担当だった2010年にビデオとオーディオのビジネスユニットが統合されて、私がオーディオも見るようになりました。まだテクニクス復活という話ではなくて、ホームシアターやサウンドバーが中心でしたが、そんなときに後のJENOエンジンの母体となるものをマイクロコンポ(SC-PMX5)に導入したり、PMX5のハイレゾ対応に取り組むなど、ピュアオーディオの動きが実を結び始めます。PMX5を国内外の評論家に聴いてもらったところ、『この音ならいっそのことテクニクスブランドにしたらどうか』と言われたことも動機付けになりました」。
井谷氏は2023年4月にCTOからテクニカル・エキスパートの立場に変わったが、今後も引き続きテクニクス事業をサポートしていくという。一方、井谷氏と10年にわたって製品開発に取り組んできた奥田忠義氏が新たにCTOに就任。JENOエンジンの開発を進めていた奥田氏は「CTOは業界の流れや技術の流れを見据えていく役割も担いますが、それだけでなく先行技術と要素技術開発の責任者も兼ねています。これからは若い音楽ファンにもテクニクスの魅力を届けていきたいと考えています」と抱負を語る。
CTOの仕事を奥田氏に委ねることで井谷氏には時間の余裕ができたのだろうか。テクニクスでやりたいことがまだたくさんあるという。「いまのオーディオは、デジタル信号処理技術が急速な進歩を遂げています。従来のアプローチではできないことがまだたくさんあって、アンプもレコードプレーヤーも『宝の山』に見えます(笑)。特にレコードは音溝に刻まれている『真実』がなにか、誰もわからない神秘性がありますよね。追求するとどんどん情報が出てくる面白さ。それがある限り、オーディオがすたれることはありません」。